この記事は約 4 分で読めます。
「一般の損益計算書」に表示されている「営業利益」や「経常利益」は業績評価においてはアテになりません。役員報酬みたいに経営者の意思で増減自在なコストである「経営コスト」が混入しているからです。
そこで、管理会計の進化型PLである「MA損益計算書」では「創造付加価値」というオリジナルの利益区分を設けて真の実力である「ビジネスが生み出している価値」を可視化するように工夫してあります。
この記事では「収益性改善の課題発見・課題解決」に欠かせないマネジメント会計(管理会計)の重要指標のひとつである「創造付加価値」について解説しています。
この記事は「中小企業向け|マネジメント会計(管理会計)の設計と運用の概要」の補足です。
PLの欠点:経常利益は本当の実力ではない
会社の業績は「営業利益」を見ればいいの?
それとも「経常利益」を見ればいいの?
何が正しんだろう?
ズバリ言います。
「営業利益」や「経常利益」で「ビジネスの真の実力」は分かりません!
ビジネスの真の実力は「創造付加価値」に現れます。
と言っても「一般の損益計算書」のどこを探しても「創造付加価値」は見当たりません。
「創造付加価値」は、マネジメント会計(管理会計)の進化型PLである「MA損益計算書」のオリジナルの利益区分であり「ビジネスが生み出している真の価値」を表す利益の概念です。
私は、中小企業の損益計算書を分析するとき、この「創造付加価値」を計算して「どんなビジネスをやってるんだろ?」とチェックするようにしています。
事例:業績は全然違うのに全く同じPL
下記の2社の決算書(損益計算書)を見比べてください。

まったく同じです。
でも、この両社の業績は「真逆」なのです。
この両社の役員報酬を確認してみると、A社は12,000、B社は6,000で、これらは「販管費」に含まれています。
上記のように「一般の損益計算書」で表すと、両社は「まったく同じ業績の会社」ということになります。
しかし、この両社の損益計算書をマネジメント会計(管理会計)の「MA損益計算書」に変換すると、下記のようになります。

単純に表現すると
「A社は、6,000の事業コストで、その3倍強の20,000の限界利益を稼ぎ出している」
「B社は、12,000の事業コストで、約1.6倍の20,000の限界利益を稼ぎ出している」
といえます。
結果としての「事業利益」は同じですが、役員報酬=経営コストを区分して「創造付加価値」を表してみると、A社のビジネスの方が断然利益率が高いことがわかります。
「営業利益」や「経常利益」が使えない理由
多くの中小企業において「役員報酬」は、それぞれの事情で任意に設定されており、また、年度ごとに増減させている会社も少なくありません。
一般の損益計算書の「営業利益」や「経常利益」は、そんな「役員報酬」に代表される「経営コスト」が混入しているから「業績評価」においては使えないのです。
(関連記事)管理会計の進化型MA損益計算書|経営コストの実務
創造付加価値から推察できること
上記の「MA損益計算書」から、次のような「推察」ができます。
- A社は、よく儲かってるので、役員報酬を高めに設定して節税してるのかな?
- A社の役員報酬をB社レベルに下げると事業利益は8,000にもなるな
- B社は創造付加価値が低いので役員報酬も低めでガマンして利益を出しているのかな?
これらの見方が正しいかどうかはわかりませんが、様々な「推察」をすることができます。このような見方・読み方ができるのが管理会計のメリットでもあります。
まとめ:ビジネスが生み出している真の価値
マネジメント会計(管理会計)の進化型MA損益計算書における「創造付加価値」について紹介しました。
- 「営業利益」や「経常利益」は「本当の実力」ではないこと
- 【事例】業績はぜんぜん違うのに損益計算書はまったく同じになる例
- 経営コストが混入しているから「営業利益」や「経常利益」は使えないこと
- 創造付加価値を明らかにすると様々な推察ができること
「一般の損益計算書」では見えない「ビジネスが生み出している真の価値」を表す「創造付加価値」は、マネジメント会計(管理会計)における特に重要な指標のひとつです。特に「収益性改善・向上」に取り組む際には欠かせません。
関連記事も含め参考にしてみてください。
もし、サポートが必要であれば、いつでも気軽に連絡ください!→「お問い合わせフォーム」
以上、お役に立ちますように!
関連記事
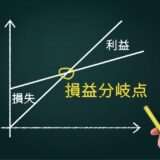
中小企業向「損益分岐点売上高」はナンセンス!の理由
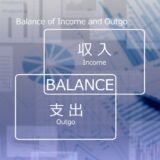
中小企業向|勘定合って銭足らず?「黒字倒産」のカラクリ

中小企業の管理会計|経営者が知っておくべき「在庫の知識」
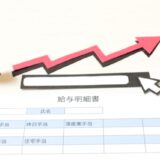
中小企業の賃金アップ|人的コスト15%アップの影響を試算する

中小企業の部門別会計|管理会計によるPLフォーマットサンプル

中小企業の部門別会計|共通経費を配賦する4つの方法

中小企業の部門別会計|減価償却費の部門別配賦の実務事例

中小企業の人的コスト比率|人件費は限界利益の40%が上限?!

中小企業の管理会計|将来への投資計画を可視化する

管理会計はホントに役に立つのか?「必要ない」という経営者

中小企業の管理会計|情報価値を高める勘定科目の”新”視点

中小企業の予算管理|「予算」は「予想」でも「予測」でもない

管理会計の活用|収益性改善|損益計算書の「黄金比率」

管理会計の進化型MA損益計算書|経営コストの実務

管理会計|ビジネスの真の実力は「創造付加価値」に表れる

管理会計の進化型MA損益計算書|事業コストの内訳

管理会計|中小企業経営者のための【進化型】MA貸借対照表

会計は「事務処理」ではなく「情報処理」であるという視点

管理会計|中小企業経営者のための【進化型】MA損益計算書

中小企業の部門別会計|設計から導入までの実務ステップ

中小企業経営者が会計に「弱い理由」と「強くなる方法」

【工務店向】弥生会計とエクセルだけで原価管理をしている事例

中小企業向|初めての管理会計「マネジメント会計入門」

中小企業の「データドリブン経営」、軸は「マネジメント会計」

中小企業が成長するために「予算管理」が絶対必要な理由


