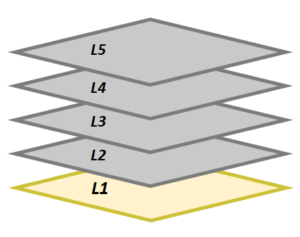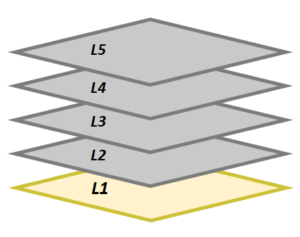成長課題を解決するために
学習し続けるチーム。
学習しないチーム。
その違いは「経営者の背中」で決まる。
チームのみんなは、勉強熱心ですか?
みんな、何のために勉強していますか?
「子供の頃の勉強方法」を引きずっていませんか?
「大人の勉強方法」で頑張っていますか?

なんの話?
勉強に子供?大人?
そんなことより・・・
確かに「熱心」とは言えないなあ・・・
どうすれば、勉強熱心なチームになるの?
さて、「勉強熱心なチーム」とは?です。
結論。
「成長課題を解決し続けるチーム」です。
なぜ、勉強するのか?
成長するためです。
「もっと役に立ちたい」からです。
これを逆さまに言い換えると・・・
- 「もっと役に立ちたい」と思わない。
↓ - だから成長しなくていい・・・
↓ - だから勉強しなくてい・・・
ってことになります。
この「勉強・学習」って、スポーツ選手の「練習」に置き換えると分かりやすいですね。
- 「チームに貢献したい」
↓ - 「でも、打率が低い」
↓ - 「打撃練習をする」
その健全な動機は
「貢献したい」
「仲間やファンにもっと喜んでもらいたい」から。
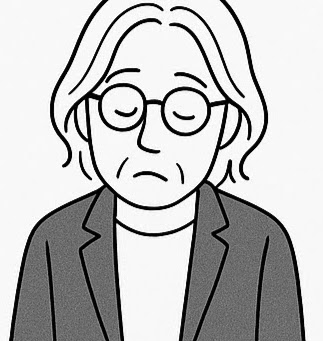
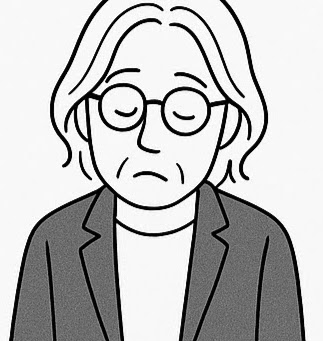
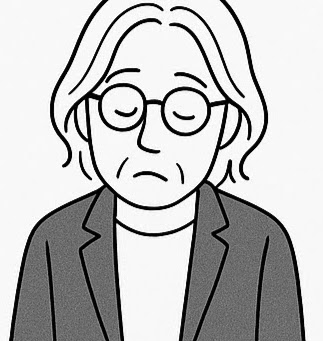
ときどき
「お金が欲しいから」
「恥をかきたくないから」
そんな動機で練習する選手もいますが
その多くは長続きしていないですね。
この話は、少々長くなるので、
またの機会にします。
難しく書き直すと
「学習は、成長課題の解決策」。
自分の強みをもっと伸ばすため、
自分の弱点を克服するための解決策。
だから、学習するのです。
その重要視点は「チームの一員として」です。
海外取引のないチームで外国語を学習しても、それは「趣味」です。
「趣味熱心」なのであって
「勉強熱心」なのではない。
常に「チームの一員として自分のあるべき姿」を鮮明にイメージし、その課題解決のための「最善策」を講じる。
これが「大人の学習」です。
ちなみに「子供の学習」は、大人になるための「土台のインプット」。
ぜんぜん目的が違います。
「物知りになること」で、
チーム貢献度が高まるなら正解。
チーム貢献度が変わらないなら、
あえて言いますが、「不正解」。
「もっと他にやることあるでしょ?」
では・・・
どうすれば、チームの学習志向を
高めることができるか?
ストレートに言います。
「経営者が背中を見せること」。
経営者の重要マインドセット、
経営者自身の「学習志向」が試されます。
経営課題の解決のために、
「常に学習している経営者自身の姿」を
チームのみんなに見せることです。
そうでないと、説得力がない。
想像できると思います・・・
缶ビール片手にバラエティ番組を見ながら「宿題やったか?勉強しろよ!」というお父さん。
お母さんのオチが恐ろしい・・・
「勉強しないと、
誰とは言わないけど
ロクな大人になれないわよ!」
子供の手本となって背中を見せる・・・
経営も同じです、たぶん。
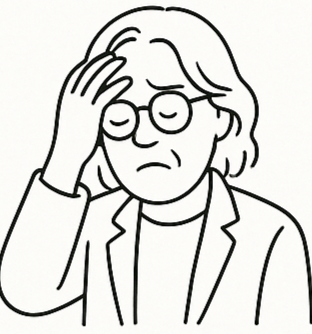
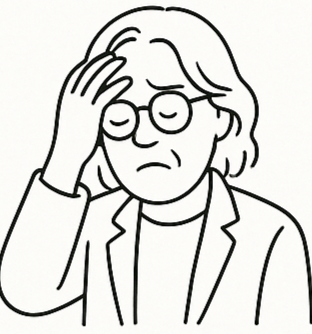
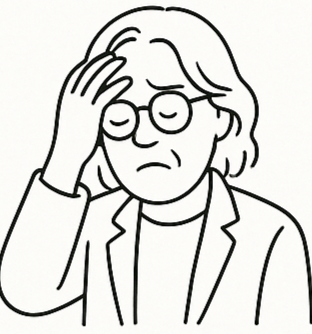
また、缶ビール片手にクドイ話を書いてしまった・・・