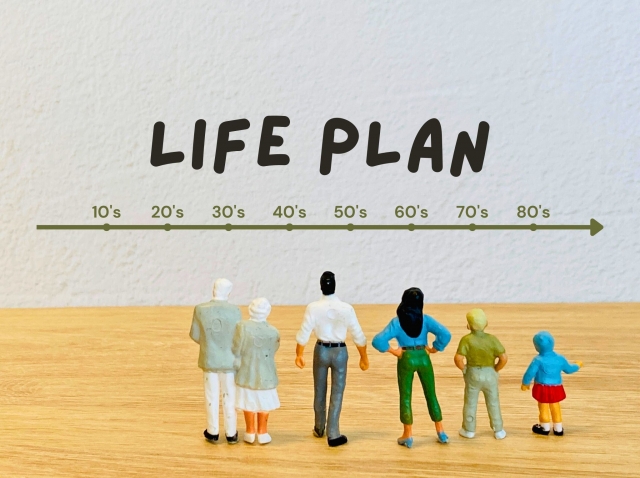私は、常々「中小企業の経営計画は経営者の人生計画という視点で考えること」とアドバイスしています。
その意味において「お金の話」は大きく、これは「会社のお金」と「経営者個人のお金」という2つの側面で考える必要があります。
これを、知ると知らぬでは「人生の損得」が大きく変わります。
この記事では、そのひとつである「中小企業のオーナー経営者のおカネ」について、最も長期的な「生涯収入」にフォーカスして整理します。
人生で大損しないように「どこまで理解できているか?」を確認してみてください。
*この記事は、更新日現在の税法等ルールによって書いています。
この記事は【保存版】成長できる経営計画の作り方「3つの新視点」の補足です。
「10人~100人規模の中小企業経営者」の方々に向けた「自己投資=経営脳トレーニングのサポート」を目的に、「もっといい会社」に成長するヒントを日々更新しています。
本記事は、35年以上にわたり税理士として中小企業経営を支援し、管理会計や経営計画を専門とするマネジメントコーチ・堀井弘三が、その現場で得た豊富な経験と知識に基づき執筆しています。
初めてアクセスしていただいた方は、「このブログについて」をまずご覧ください。
執筆者、堀井弘三のプロフィールはこちらです。
【起点】
「いくら必要か?」から始める
さて、「いくら必要か?」から始めましょう。
これは、極めてプライベートな話なので、人によって様々です。
すでに「ひと財産」を持っている人なら「もう、これ以上要らない」と思うかもしれません。
反対に、大きな負債を抱えている人なら「生活費以上のお金が必要」かもしれません。
独り身の人、家族の多い人の違いによっても必要資金は大きく変わるでしょう。
いずれにしても「その出所」は・・・
- 現役時代は「役員報酬」と「配当」
- 引退後は「退職金」と「株式の売却(払い戻し)対価」
・・・の4つです。
オーナー経営者の場合、「生涯賃金(給与+退職金)」に加えて、自社株からの配当や、その株式の売却(払い戻し)対価までが「生涯収入」に含まれます。
*さらに株式等の投資運用や、サイドビジネスの副収入などの「枝葉」が生い茂る人もいますが、この記事では、すべてのオーナー経営者に共通する「4つの出所」に限定して整理します。
【源泉】
生涯収入の4つの「出所」
前述したように、オーナー経営者の「生涯収入」の中心は4つ。
- 役員報酬
- 自社株からの配当
- 役員退職金
- 株式の売却(払い戻し)対価
それぞれの特徴について、基礎知識を確認しておきましょう。
役員報酬と自社株評価と
その税金
役員報酬の増減は、ダイレクトに「会社の業績」にリンクし「表裏の関係」にあります。
役員報酬を大きくすれば、その分だけ会社の業績は減少します。
反対に、役員報酬を小さく設定すれば、それだけ会社に利益が残ることになり「内部留保」が溜まりやすくなります。
さらに、この「内部留保」は「株価」を左右します。
「内部留保」が大きくなれば「株価」が高くなります。
つまり、意識していない人が多いのですが「役員報酬」の金額設定は「自社株の評価」に連動していることを忘れないようにしましょう。
この「自社株の評価」が、将来の「相続税・贈与税・所得税」に影響します。
一般的に、月々の「役員報酬」は、税法ルールを慎重に検討し「税メリット」が最も大きい金額に設定されます。
受け取る個人には「所得税・個人住民税」が課税され、さらに「社会保険料」の負担もあります。
会社の利益には「法人税と関連地方税」が課税されます。
さらに、個人の税金は「超過累進課税」、会社の税金は「平均課税」であることも、税金の基礎知識として知っておく必要があります。
この違いが「税メリット」に大きく影響します。
自社株からの配当
中小企業で配当を実施している会社は少数派ですが、その理由の多くは「デメリット」でしょう。
会社側で考えた場合、「役員報酬」で支払えば「損金」になりますが、「配当」で支払っても「損金」にならないからです。
また、中小企業の場合「配当実績」が「自社株評価」に影響することも配当しない会社が多い理由でもあります。
役員退職金
会社の清算も含め、経営者としての引退は「取締役を退任する」ということですが、その際に「役員退職金」を得ることができます。
税法には「過大役員退職金」という損金上限のルールがあるため、その金額設定においても「節税シミュレーション」を行うことが一般的です。
会社側においては「損金計上できる範囲」を検討し、一方、受け取る個人側においては「手取り額」をシミュレーションします。
ちなみに、退職金を受け取る個人は、在任期間に応じて「退職所得」を計算し、その上で半額分離課税になるため、同額の「役員報酬」を受け取ることに比較して、その税負担は低くなります。
極端な(机上の)想定をすれば、役員報酬は最低限で設定しておき、それによって蓄積した内部留保を退職金で受け取れば(法人側の課税を考えなければ)「手取り額を最大化」することも可能です。
逆に考えれば「(高課税の)役員報酬」を高額に設定することで内部留保を蓄積せず、「(低課税の)退職金はナシ」とすれば「手取り額は最小化」してしまうことになります。
また、損金計上の有無に関わらず「会社から退職金を支払う」ので、内部留保が減少し、それに伴って「自社株評価」が低くなります。
極端なケースとして、内部留保を全額退職金として支出すれば「株価」はゼロになることもあります。
自社株の売却・払い戻し
あなたの会社の「自社株の評価額」を知っていますか?
ほとんどの経営者は「知らない」「気にしたことがない」と言います。
キケンです。
「直近決算時点での株価評価」を顧問税理士に依頼しましょう。
会社の業績によって、株価評価は常に動きますが、まずは「基準点」知っておくことをオススメします。
この「基準点」を知っておくだけで「将来のおおよそのイメージ」をすることができます。
「まったく見当が付かない」という状態とは違って、経営者なら「いろんな気付き」があるはずです。
この「自社株」は「経営者の出口:2つの選択肢=承継か?解散か?」によって、その取扱いは変わりますが、いずれのケースであっても「株価評価」が影響します。
特に、業績好調で、かつ「後継者に事業承継」を予定しているのであれば、年々評価額が高騰していき、その「相続」の難易度が高まるので、早い段階での「想定」がとても重要です。
(関連記事)経営者の引退・・「出口」を知らない経営者はいずれ後悔する
【図解】4つの「出所」関連図
以上「4つの出所」を解説しましたが「ややこしいなあ・・・」と感じられたと思います。
改めて、それぞれの関連をイメージにしたので確認してみてください。
*このイメージ図は説明を簡略化するため「税金」は記載していません。
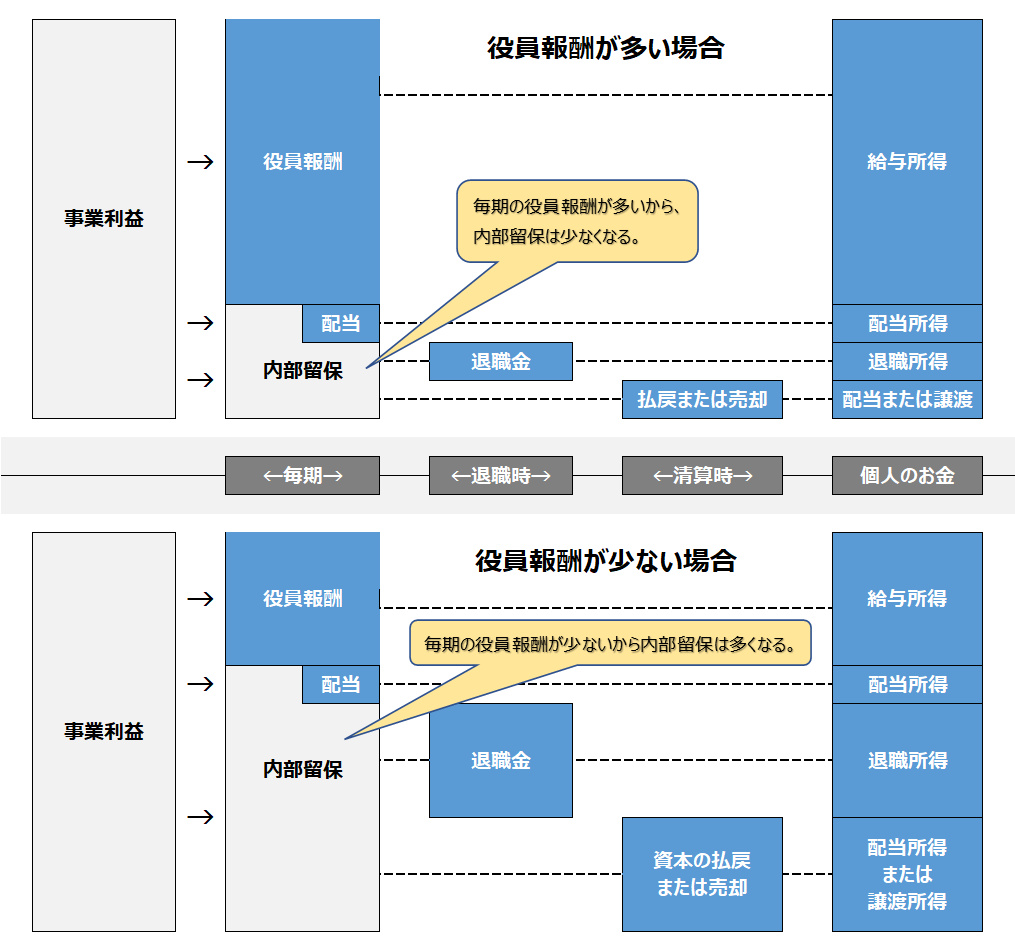
【連携】
信頼できる税理士と二人三脚で
さて、「ややこしいなああ・・・結局、どうすればいいの?」と、かえって混乱されたかもしれませんね。
冒頭にも書いたように、すでに持っている貯蓄や負債、それぞれが必要としているレベル、家族構成など、それぞれの「変数=計算要素」に違いがあります。
したがって、この「生涯収入の最適化」の答えは「百人百様」です。
また、毎年改正される税法にも大きな影響を受けるので、私のアドバイスは「信頼できる顧問税理士と連携すること」です。
この相談に応じられないような税理士なら、今すぐ「新しい別の税理士」を探しましょう。
「人生の損得」に影響するからです。
【要点】
後悔しないための人生の予算管理
さて、どうですか?中小企業のオーナー経営者の「生涯収入」を「4つの出所」に分類して整理してみました。
これらへの向き合い方が人生の損得に大きく影響します。
まさに「人生の予算管理」に他なりません。
もし、サポートが必要であれば、いつでも気軽に連絡ください!
以上、お役に立ちますように!