経営脳の第5レイヤー、
センス。
経営者の「感じ方」で
会社の「価値」は大きく変わる。
「センスが良い考動」か?
「センスが悪い考動」か?
それは、経営者の「感じ方」次第。
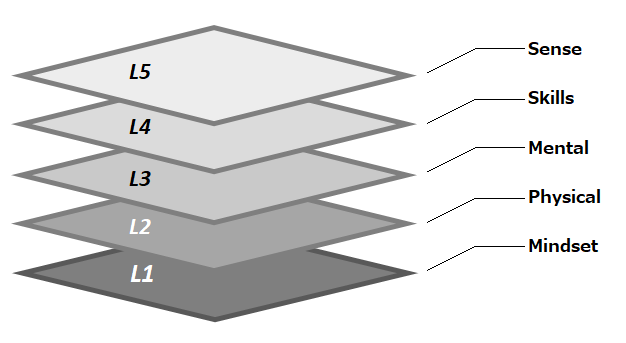
10人~200人規模の中小企業経営者の「自己投資=経営脳トレーニングのサポート」を目的に、「もっといい経営者」「もっといい会社」に成長するヒントを日々更新しています。
40年近く税理士として中小企業経営を支援し、経営計画や管理会計、組織作りを専門とするマネジメントコーチ・堀井弘三が、その現場で得た豊富な経験と知識に基づき執筆しています。
初めてアクセスしていただいた方は、「このサイトについて」をまずご覧ください。
【イントロ】
価値の優劣が決まる

先に書いておきますね。
本稿は「ビジネス」の話です。
「芸術的なセンス」の話ではありません。
ビジネスは「価値創造活動」と言えます。
「金銭」を「他者の価値」と交換すると「コスト」が発生します。
「価値」の優劣によって「交換比率」が決まります。
「自社の価値」を「金銭」と交換すると「売上」が立ちます。
この「価値の優劣」を左右するが「経営者のセンス」です。
「センス」が良ければ、交換比率が高くなり「より高く」売れます。
「センス」が敏感だと「目利き=他者の価値評価」が正確なので「適正価格」で買えます。
だから、「センス」に課題があると、「価格競争」や「コスト高」という経営課題を抱えることになります。
つまり「センス」は「違い/差」を感じ取る力ということができます。
私たちは、この理屈を特に意識することなく・・・
「お!センスあるやん~」
「センスないわ~!」
「ぜんぜん、フツーやん」
・・・と日常的に「誰かのセンス」を評価しています。
「経営者のセンス」は良いに越したことはありません。
「経営脳の第5レイヤー:センス」について深堀りしてみましょう。
【構造理解】
経営脳における位置づけ
センスは、経営脳の5つのレイヤーの最上層(Layer5)に位置します。
定義しておきましょう。
センスは「差を感じ取り、価値創造の起点となる感性」。
価値の差を捉え、カタチに変換する手助けをする能力です。
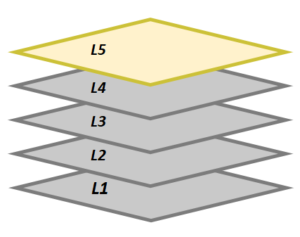
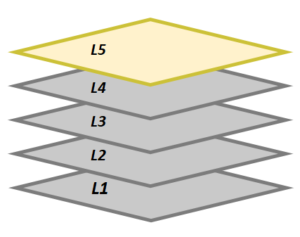
センスは、いわば「アタッチメント」のような特徴があります。
- マインドセット:考え方がちょっと違う
- フィジカル:カラダのメンテ方法がちょっと違う
- メンタル:ココロのメンテ方法がちょっと違う
- スキル:アウトプットがちょっと違う
このように、下層の4レイヤーに「違い」=「差」をつけるのが「センス」です。
「センスの良し悪し」で、
「良い方向の差」になることもあれば、
「悪い方向の差」になることもあります。
「センスの強弱」で、
「大きな差」になることもあれば、
「微妙な差」になることもあります。
反対に、下層の4レイヤーの「おかげ」も小さくありません。
他のレイヤーが整っていないと、そもそも「差を付けよう」という考動に及びません。
だから「センスが良い人」は「感性」を支える下層の4つのレイヤーが前提として整っているものです。
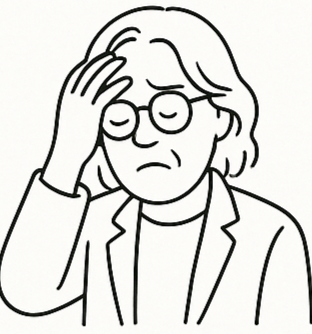
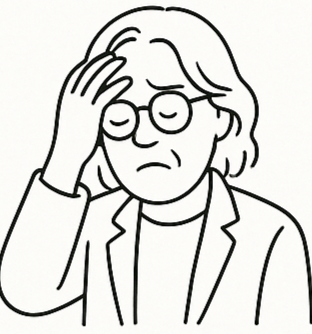
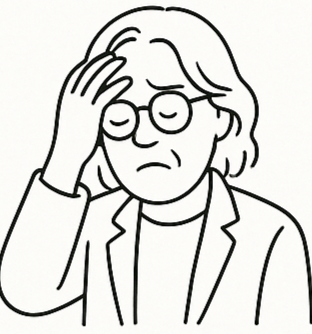
これを裏返すと「せっかくの感性」を持っているのに、下層4レイヤーに課題があるので「埋もれている」ということもあり「あ~あ、もったいないなあ・・・せっかく、いいセンスを持っているのに」と思うことが少なくありません。
【重要視点】
センスの3つの仕事
これは「感覚そのもの」ではなく「経営脳」の話です。
「センスが良い・悪い」ではなく
「センスをどう磨くか?」。
そのために「センスの正体」の解像度を高めましょう。
「センスの仕事」を3段階に分けてみました。
1)感知:差に気付く
複数の対象を見て「何かが違う」と気づく。
うっかり見逃してしまいそうな「ちょっとした差」を見逃さない。
「同じに見える人」と「違いが見える人」。
この「ちょっとした差」は「ちょっとした意識」で、感知しやすくなります。
2)判断:良否を見極める
感知した差や違いを評価し
「どちらがいいか」を見極める。
「なんか違う」ことに気付いて
「これが違う」と特定すること。
特定すると
「こっちがスキ・こっちがキライ」と、判断しやすくなります。
3)要件化:スキルに引き渡す
次が「仕事」です。
「判断した差」を、カタチにするために「スキル」に伝達。
「価値ある差」を、
「こうすれば改良できる」
「こうすれば実現できる」というように
「カタチにする具体的な方法」に落とし込む。
そうすれば
「イイモノ・イイコト」が実現します。
この3つが「センスの仕事」です。
実際に「実装」するのは「スキルの仕事」。
「こうすれば!」まで感じても
「スキル(=実現能力)」が受けきれなければ
「アイデアどまり」、という理屈です。
【相違確認】
スキルとの違い
「スキル」と「センス」の違いが「あいまい」になることがあります。
以下「ざっくり」比較しておくので参考にしてください。
- スキルは「できる・できない」もの
- センスは「いい・わるい」もの
- スキルは「知ってる・知らない」もの
- センスは「感じた・感じない」もの
- スキルは、経験や学習の量と比例するもの
- センスは、経験や気持ちの質と比例するもの
- スキルは、人の評価が分かれないもの
- センスは、人によって評価が分かれるもの
【優先要素】
8つのテーマでチェック
さて、各論です。
センスを磨くために、まず現状を確認することから始めましょう。
ここでは、経営者のセンスにおいて特に影響力が大きい8つのテーマをリストアップします。
センスは、これらの「総合力」と言えます。
- Check1:好奇心
- 差や違いに対して積極的に興味や関心を向ける力
- 好奇心がなければ、そもそも「差」に気付かない。「これ、なに?」がセンスの起点
- Check2:移入力
- 他者の好き嫌いの評価軸を正確に感じ取る力
- 「相手にとっての価値」を理解するために、「相手のものさし」で観察する
- Check3:観察力
- 対象を見続ける力
- 「ざっと・さっと」ではなく「差」が見えるまで継続する
- Check4:緻密力
- 対象の細部にまでこだわる力
- 「ざっくり」「おおまかに」ではなく、「かすかな違い・わずかな差」を詰める
- Check5:比較力
- 複数を比較し、その違いを具体的に抽出する力
- 「なんとなく違う(感覚)」を「ここが違う(言語)」に変換する
- Check6:発想力
- 新しいアイデアや独自の視点を生み出す力
- 偶然ではなく、意図して「違うモノ・違うコト」をアウトプット
- Check7:構成力
- 感知した複数の要素を組み合わせて、より高い価値に変換する力
- 組み合わせ方の差や違いで、新たな価値を構成する
- Check8:執着力
- 安易な妥協をせず、求めている解に至る力。
- 「まあ、これでいいか」で終わらせない粘り強さ
【課題抽出】
センスを自問自答
8つの要素について、自分自身に問いかけてみてください。
- 好奇心:周りに気になるものは多いか?
- 移入力:相手の気持ちに興味があるか?
- 観察力:ずっと見続けられるか?
- 緻密力:些細なことが気になるか?
- 比較力:違いを言葉にしているか?
- 発想力:差や違いを出すことがスキか?
- 構成力:組み合わせを変えているか?
- 執着力:しつこいか?
「できている」と「できていない」を仕分けして、課題を明確にしましょう。
【参考まで】
私が心がけていること
ここで公開するかどうか、迷ったのですが・・・
私はセンスを高めるために次のようなことを意識しています。(順不同)
もし、参考になるならと思って公開します。
- 自分をあきらめない=自分のセンスはきっと良くなるという可能志向
- 「あの人のようになりたい」というセンスがいい憧れの人のマネしてみる
- 他の意見に左右されることなく、自分の素直な気持ちでスキキライをハッキリさせる
- 服や持ち物、振る舞いなどのオシャレに気をつかい、褒めてほしい人に褒めてもらえるように努力する
- 「(いい意味で)みんなと違う」「ヘンやな」という他からの評価を喜ぶ
- カッコいい・カッコ悪いにこだわる
- 話す機会があれば、必ず「オチ」を付ける(関西やし?)
これらは「私の場合」です。
「あなたなりの方法」を探してみてください。
【要点整理】
優しさに敏感な経営者になる
さて「経営脳:第5のレイヤー:センス」について整理しました。
- センスとは「差を感じ取り、価値創造の起点となる感性」であること
- センスには「感知→判断→要件化」の3つの「仕事」があること
- 8つの要素(好奇心・移入力・観察力・緻密力・比較力・発想力・構成力・執着力)の総合力であること
- センスは、下層4レイヤーのアタッチメントであると同時に、それらに支えられている「持ちつ持たれつ」のレイヤーであること
目的は「もっといい会社」に成長することです。
経営者の「感性」が、
良くも悪くも、
会社の「価値」に大きく影響します。
「芸術的なセンス」とは違い
「ビジネスでのセンス」は先天的なものではありません。
「意識と努力」でセンスは磨けます。
本稿を参考にして、ますます研ぎ澄ませてください!
お役に立ちますように!



最後に、もう一言「念押し」。
「センス」は「相手にとっての価値」。
「センスええなあ!」という評価は相手がするもの。
相手のスキキライやニーズを無視して
「センスええやろ?」と「どや顔」するのが、いちばん「センスのないやつ」(笑)。
いつも「相手のことを思い続ける」だけで「感度」は変わります。
「人にやさしい経営者」になることが、実は「最大のコツ」です!

